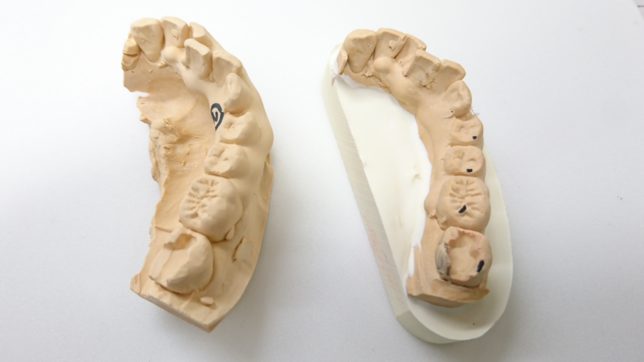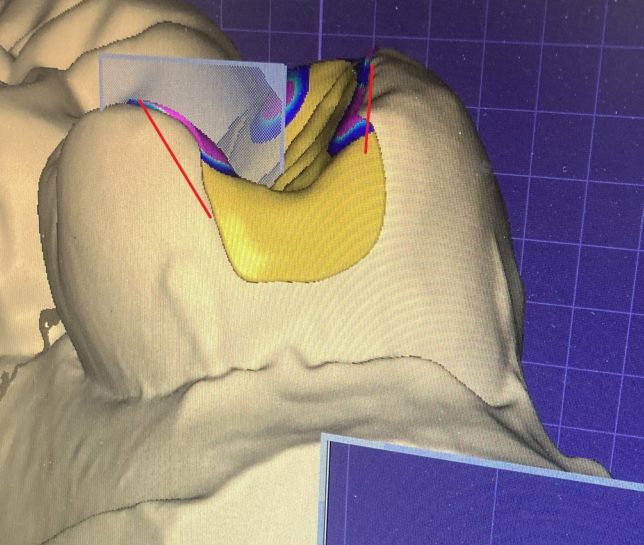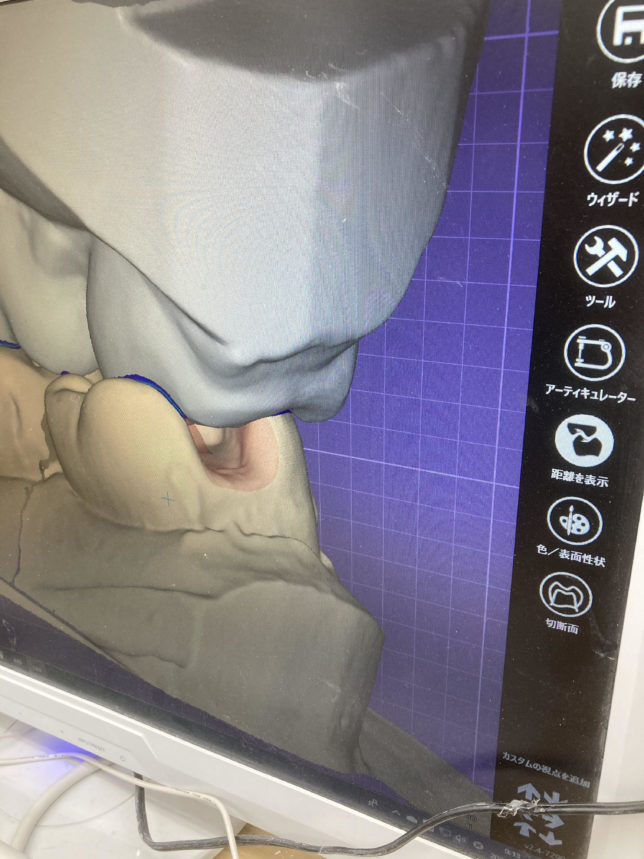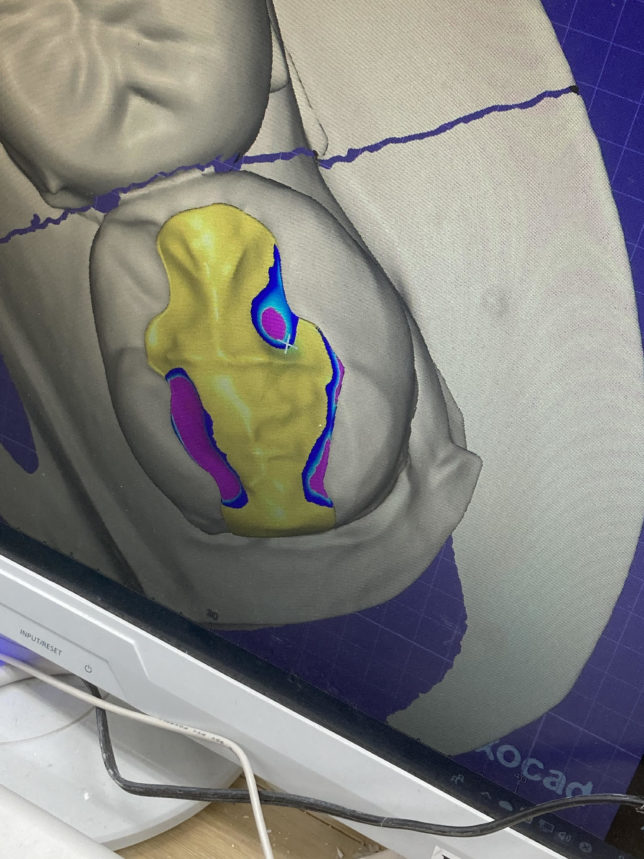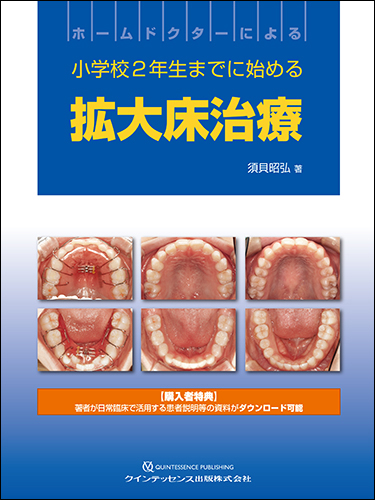宝塚市の歯医者、笹山歯科医院 院長の笹山です。
先日、診療室のポストに患者さんからの手紙が入っていました。
お手紙を頂いたのは90歳のおばあちゃんで、父の代から含めて50年近く通院してくださっている患者さんです。
しばらくお見えになっていなかったので、どうされているのかと気にかけていたのですが、お手紙にはご親族の元へ引っ越しされたとの事で「転居先ではもう歯医者には行っていないけれど、教わった歯みがき方法で毎日一生懸命、歯を磨いています。」とあり「これからも歯で困っている人達を助けてあげてください。」とも書いてくださいました。
日々色々なことがありますが、そんなことも忘れてしまうほど嬉しかったです。
1人でも多く患者さんに、信頼して頂けるようこれからも頑張ります。
ちなみにこの患者さんは、5年前にもブログに書かかせて頂いた方です↓