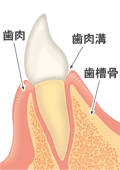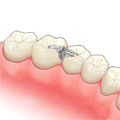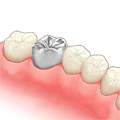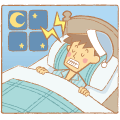突然ですが歯間ケアしてますか?
デンタルフロスや歯間ブラシのことです。
歯と歯の間の虫歯は虫歯が出来てから穴が空くまでに時間がかかります。
穴が空いた時に、感じる症状は「冷たい物が凍みる」「食事すると歯が痛い」です。
ひどい場合は神経を抜かないといけないことも・・。
さて、下の歯は歯と歯の間が虫歯です。結構大きいです。どこだか分かりますか?

ここです↓ こんなに大きな虫歯になっていました。

全部取りきった後です↓ 結構な穴が空きました。隣の歯もかなり怪しかったのですが、虫歯じゃなくて一安心

歯と同じような色の樹脂で詰めました。1回で治療終了です。

これらの治療過程の画像は歯間ケアの大切さを理解して頂くために、大型液晶モニターにを映して患者さんに見て頂きます。
別ケースです↓ どこが虫歯だか分かりますか?

削っている途中

むし歯をほぼ取り切った状態↓もう少しで神経まで到達しそうな深さでした…。


治療後

歯と歯の間の虫歯は大人虫歯の好発部位ですので、歯間ケアは必須です。
また歯と歯の間は、歯の噛む面や歯の付け根など他の部分と比べて2.5倍以上歯周病が悪化しやすいというデータもあります。
歯間ケアは虫歯や歯周病予防にもとっても大切です。
「歯間ブラシのサイズが合っているか分からない。」
「歯間ケアしたいけど、上手く出来なくてやめた。」
「以前フロスを使っていたけれど、面倒だった。」
などありましたら何でもご相談ください。
最適なケアグッズで楽ちん継続可能な歯間ケアを提案いたします。
以上「歯と歯の間の虫歯は気づくまで時間がかかる」でした。
皆さまのお口の健康の参考になれば幸いです。
宝塚市の歯医者 笹山歯科医院