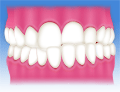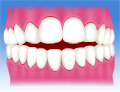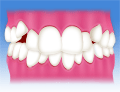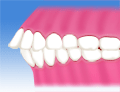日曜日。朝から大阪へ。

デンタルショーに行ってきました。車でいうモーターショーのようなもので
最新の機材や診療器具を目で見て触れる事が出来る少ない機会です。
今回は見たいもの、聞きたいことを決めて行ったので、効率的に会場を回れました。
お世話になっている業者さん方ともお会いしましたので色々話を聞けました。
2時間ほどで散策を終え会場を後にしました。
その後、なんばへ。
大阪に行った時、良く行くラーメン屋さんの「のすた」です。

関東にラーメン二郎というラーメン屋さんがあります。
横浜に住んでいて時にはまってしまい、関東一円にある直系の店30店以上すべてに行ったほどです。(仙台店と札幌店にも遠征しました(^_^;))
そのラーメンに似たラーメンを出すお店をラーメン二郎インスパイア系といいます。(二郎非公認です)
関西には二郎の直系店はありませんが、インスパイア系は何軒かあります。
そのほとんど行きましたがここが一番おいしいと個人的に思っています。
東京の大崎に本店があったお店で、麺やスープに作りの丁寧さが感じられます。
朝は天気が悪かったのですが、昼ごろからは天気が良くなり、気持ちよく過ごせた1日でした!